令和2年3月13日
本サイトの情報は、正確であるよう努めておりますが、万が一、情報が不正確であったことによる損害について、一切の責任を負いかねます。
業務を円滑に進めるための情報共有ツール
世の中では依然として新型コロナウイルスが猛威を振るっており、時差出勤やテレワークを導入する企業も増えてきています。このように勤務形態が変化していく中で業務を円滑に進めるためには「情報共有」が重要となっていきます。今回は情報共有ツールについてお伝えします。
情報共有ツールの種類
①共有フォルダ
共有フォルダは、ネットワークで接続された1台のPC中につくられた、ネットワークの参加者がアクセスできる場所のことです。ビジネスで一般的に使われているWindowsには、この共有フォルダを作る機能が標準で用意されています。
②クラウド
クラウドは、インターネット全般を表す言葉ですが、情報共有の場合はインターネット上に用意された、ファイル共有のための場所やサービスを指します。「クラウドストレージ」や「オンラインストレージ」とも呼ばれ、容量で各社がしのぎを削っています。容量や共有するユーザー数等の制限があるものの無料で使えるサービスも多数あります。DropboxやOneDrive、Googleドライブなどが有名です。ビジネスで使うことを前提とした有料版は、各社1万数千円/年の料金設定となっています。
③ファイルサーバ
ファイルサーバは、社内ネットワークに追加する形で接続される、ファイル共有専用のストレージ(記憶装置)を指します。NAS(ナス:Network Attached Storageの略)もファイルサーバの一種と考えてよいでしょう。ネットワーク内のPCから共通して使える外付けHDDのイメージで、手軽に使えるのが魅力です。利用にはファイルサーバ本体を用意する必要がありますが、NASであれば10TB程度の容量の製品が数万円で購入可能です。
(参考図書 日本実業出版社 月刊「企業実務」)
○担当者コラム
共有フォルダを外部からアクセス可能にする為には複雑な設定を行う必要があり、専門家に作業してもらう必要があります。
クラウドは24時間、世界中のどこからでも必要なファイルやデータにアクセス可能ですし、費用負担が少なく導入できますが、情報を社外に出さないことを定めているのであれば利用はできません。
ファイルサーバやNASは、共有フォルダとクラウドの中間に位置します。設定によって社外からのアクセスに対応することも可能ですが、基本的には社内からのみのアクセスに対応し、通常は24時間ファイルやデータの共有が可能です。

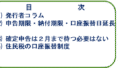

コメント