令和元年8月19日
本サイトの情報は、正確であるよう努めておりますが、万が一、情報が不正確であったことによる損害について、一切の責任を負いかねます。
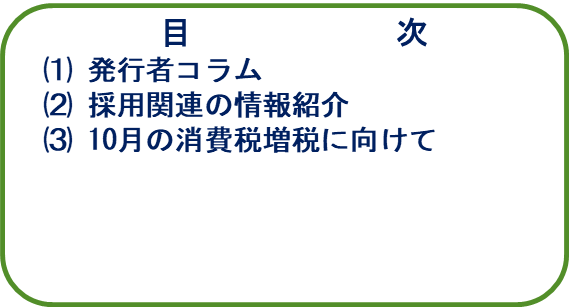
⑴ 発行者コラム
お盆休みは家族で道の駅ふぉレスト君田に行きました。ここは宿泊もでき、コテージもあるので子供のいる友人ともよく利用しています。近くに君田こども遊園地というところがあり川遊びができます(遊園地というか小さな公園)。小さい魚を網で取ったり、浮き輪で泳いでいる子供がたくさんいます。木陰がたくさんあるので親も困りません。テントをたててBBQをしている人も多いので小さな子供がいる人は泊りがけでもおすすめです。無料です。
知人からメダカ・金魚をもらったり、金魚すくいで取った金魚を育てています。金魚すくいで子供が取った金魚を家の外に置いた80ℓプラ舟で育てて1年経過しました。2cm程度しかなかったのに今では10cmを超えています。家の中で飼うと水替えが大変で躊躇しますが、外で飼っているので水替えが雑にできて世話が楽です。餌もあげれなくても1週間程度は生き延びます。癒されます。おすすめです。
消費税10%が完全確定したのかよくわかりませんが、この10月から消費税率10%になるのはほぼ間違いなさそうですね。軽減税率も始まり、ややこしくなります。飲食店で店員さんに持ち帰りと言った上でイートインコーナーで食べる人が続出しそうな感じがします。
盆休み中に採用関係などの本を何冊か読んだので、次ページ以降簡単に情報共有します。といってもかなりの情報量なので文字ばっかりです。斜め読みしてもらって、興味のある箇所だけでも読んでもらえると幸いです。
⑵ 採用関連の情報紹介
採用に困っている会社は多いと思います。私が最近読んだ採用関係の本などから自分なりにざっくりまとめた情報を共有します。文字ばっかりです。
①採用のルール
【採用の心得】
・人材要件は、「必須要件」「優秀要件」「ネガティブ要件」「不問要件」という4つのカテゴリに分けて考える。
必要要件…自社で働く上で欠かすことができない要素(この要件を満たさなければ不合格)
優秀要件…不可欠というわけではないが、あるとよい要素。入社の時点で必須ではない(この要件を満たさないからといって不合格にしてはならない)
ネガティブ要件…「ない」ほうが望ましい要素。自社に不適合の人がもつ要素(この要件を満たす人は不合格)
不問要件…一般的には大事とされる場合が多いが、自社では問わない要素。(この要件が不足していたとしても不合格にしてはならない)
・人材要件は優秀要件の列挙に陥りがち。「そんな人材はなかなかいない」と人材確保に苦しむことになる。
・人材要件を定義する際には、必要な情報を集める。社内インタビューやアンケートにより、経営者・ハイパフォーマー・現場と膝をつめて話し合うこと。言葉の定義は人によって異なるため注意。
・人材要件の例
必要要件…素直さ(人の意見を受け入れる姿勢があると、職場のメンバーにかわいがってもらえる。)、優秀要件…分析の能力(入社時になくても会社に適応できるが、あると早く戦力になる)、ネガティブ要件…思いやりの欠如(自分の利益を重視し、相手の立場で考えられない人は、顧客との信頼関係を築けない)、不問要件…志望度(自社に対する志望度が高くなくても、活躍できる)
【求職者を集める】
・ネガティブな情報もさらけ出すほうがよい(RJP…現実的な仕事の情報の事前開示)。次のようなプラス効果があるといわれている。
❶入社後の離職を回避できる
採用時に語られなかったネガティブな現実に直面すると「聞いていた話と違う」と落胆する。このリアリティ・ショックが強いと「離職意思」が高まる。これを緩和できる。
❷企業イメージが向上する
ネガティブな情報までも提示する企業のスタンスに対して、オープンな会社だと魅力を感じ、企業イメージが向上する。
【応募者から選ぶ】
・求める能力のリストはあっという間に膨れ上がるが、このリストに該当する人材を探すのは現実的ではない。過酷な獲得競争が待っている。
・選考で見極めるべき能力を見直す。本当に見極める必要のあるものを絞りこむ。選考で見極めが必要なものを明確にするために次の2つの観点を確認する。
❶入社1・2年目を生き残るために必要な能力
1・2年目は会社に適応するのに苦しみやすい時期。この時期を乗り越えるのに必要な能力を考え、選考で見極めるべき能力として設定する。
❷入社3年目以降にも必要で、育成が難しい能力
入社後に育成可能・学習できる環境が社内に存在するものより、育成が困難なものが重要。顧客志向に基づいて行動すること、口頭でのコミュニケーションの上手さは入社後に育成できるといわれている。
・入社前に最低限持っていてほしい能力と入社後に育成できる能力を明確にする。育成できる能力は人材要件に入れない。入社1・2年目を生き残るための能力と3年目以降、育成困難なものを人材要件に入れる。
・企業が自社の社風と応募者は合っていると言葉にして応募者に伝えること。社風を言語化する際には、革新性・安定性・成果志向・集団志向、の4つの軸で考える。
②採用の思考法
【採用をなめてはいけない】
・どんなに磨いても、石ころはダイヤモンドにはならない。間違えた人を採用したら、どんなに教育してもムリなものはムリ
⇒人材採用は限られたパイの奪い合い・競争であり、採用活動を一生懸命にやる必要がある。
・経営目標を達成させるには、採用が本当に大事。育成には限界がある。素材の目利き力こそが経営力。採用を間違えたら「爆弾」を背負うようなもの。採用ミスによる組織へのダメージは計り知れない。付加価値を生み出すいい人材を採用しないと意味がない。
・完璧な会社など存在しない。完璧を求めるのではなく、他社よりも優れている点がどこかを突き詰めて考えれば、おのずと自分の会社に自信が持てるようになる。
【いい採用を実現させるために案外やっていないこと】
・採用基準を下げていいのは次の2パターンのいずれか。
❶今後、お客様に提供する価値基準を下げるつもりであること
❷戦力化までの育成シナリオが万全にあること
・企業が採用基準を下げるということは、入社後の教育をセットで考える必要がある。
・3つの覚悟があれば採用基準を下げてもいい
❶育成する覚悟・コストを払う覚悟(社内のリソースを対象者に投資すること=金銭的コストだけでなく、既存社員の社員も育成に費やす。数値では算出しづらい精神的なコスト(根気)もかかる。)
❷待つ覚悟(求める基準にもっていくまでには時間がかかる。覚悟があっても、いつまでを「育成期間」とするか定義づけし、期限から逆算した育成プログラムが必要である。)
❸芽が出ない覚悟(育成する覚悟があって、基準に達するまで待つ覚悟があっても芽が出ないこともある。)
・採用の質を下げても、お客様への提供の質は下げられない
・採用するうえで一番やってはいけないこと=採用基準を下げること
・先天的、後天的能力を見抜く。人間の「意識レベル」には5つの階層がある(ニューロロジカルレベル)。
①アイデンティティ(自己認識):「私は~である」、②信念・価値観「私は~という考え方を大事にしている」 、③能力「私は~することができる」 、④行動「私はいつも~している」 、⑤環境「私は~に所属している」
それぞれのレベルは互いに影響し合い、各階層に変化があると、他の階層にも変化が現れる。
・特に変化させるのが難しいのは①アイデンティティ(自己認識)と②信念・価値観。これを外的な力で変えるのは非常に困難を伴う。
・人間は過去の体験の「インパクト×回数」でできている。①②を変えるには相当なインパクト×回数が必要となる。
・人の意識を変える手順…最底辺の⑤から変えていく。⑤場ができていれば、④行動は変えられる。人間は周囲の環境や場に影響を受けやすい。周りがやっていれば自分もやらないとまずいと思い実行する。
その場にいる人があたりまえに行動すべきことをルールとして設定してまずは行動してもらう。行動していればほめられ、行動していなければ叱る。この行動を繰り返していけば習慣化し、行動を繰り返せば実力がつく。そしてできなかったことができるようになる。③能力は④行動により身に着く。
・コミュニケーション能力は、入社時には必要ない能力。コミュニケーションをうまくとる方法を知らないことがほとんど。教育や努力でできるようになる。
・上記①アイデンティティ、②信念・価値観は、生まれて数十年で身に着けてきたものであり、入社後の教育・努力等で簡単に変えられるものではない。いくら教育しても無理なものは無理である。よって、採用基準の設定においても、「性格のマッチング」「価値観のマッチング」は非常に重要なファクターとなる。
・会社にも性格がある。経営理念・ミッション・ビジョン、どんな社員がどんな理由で働いているかといった情報は、その会社の性格を表す。これまで事業を展開してきた歴史のなかで大切にしてきた考え方、価値観である。こういう自社の価値観に合う人材かどうかは、外せない採用基準といえる。
・就職先企業を決めた理由のトップは、「社会貢献度が高いこと」(2019年32.1%)。求職者は自身の価値観と企業の価値観があっているのかどうかを重視する傾向にある。
・価値観が合う人を採用する。採用基準を満たさない人は絶対に採用しない。採用人数は妥協しても、採用基準は妥協してはならない。
・中小企業こそ、「経営理念」など共通の目的や価値観を掲げ、これに共感する人を集め、組織にしっかり浸透させる必要がある。
・採用基準を設定して、それが自社に必要な理由(論拠)も言語化することで、個々の面接官の主観に左右されないようにする。
【いい採用を実現させる具体的なステップ】
・自社を知ってもらう。採用でもマーケティングでいう4Pを考える。
Product:自社そのもの、Price:自社で働くことで得られる価値、Place:自社の採用基準に合った人材、Promotion:自社を知ってもらう活動
・採用活動で重要視する施策(2020年新卒)は、インターンシップ(44%)、自社セミナー・説明会(42%)であり、「リアルな接触」が重要と捉えられている。
・会社説明会でやってはいけないこと=説明すること。求職者が求める知りたい情報とは、「一緒に働くのは、目の前のこの人たち」という情報。現場社員を登場させて話をさせること。会社説明会の参加者が知りたい情報は「社風」である。
インターネットだけではわからないリアルな情報を求めている。社員の何気ない表情、社員同士の会話、日常が垣間見れる情報である。
・知名度の低い会社は会社説明会を開いても人が集まらない。コンセプトを変えて1対1か1対2の「個別就職相談会」という形がおすすめ。求職者の課題、ニーズを確認しながら、自社が合うところ、合わないところをリアルに紹介していく。お互いのことを十分に理解した上で選考に進むことを提案する。
・エントリーは量より質を重視する(量を増やすと時間的・金銭的・精神的コストが増加したうえに、一人一人の単純接触回数が減り、入社動機を高められなくなり負のサイクルに陥ってしまう)
・選考プロセスのなかに、リアルな「中身」に触れてもらう機会を作り、「この仕事を、この仲間と、この環境でやりたい」と決断できるよう、情報提供をする
③中小企業は無料のハローワーク(+Indeed)をうまく使う
【採用につながる求人登録の仕方】
・「職種」の記載にこだわる。一番最初にスマホ等で表示されるのは「職種」であり、仕事の内容ではない。会社名でもない。最初の14文字しか表示されないスマホアプリもあるため、大事なことを最初の14文字に記載する。
・具体的に28文字(がMAX)で、職種を読んだだけで仕事の内容が分かるようにする。職種欄で、誰に、何を、どのように、働く側のメリットを訴える
・事務所登録シートでは、「事業内容」で会社の信頼性をアピールする。具体的かつわかりやすく。どのような事業を行っており、主要な商品・サービスは、経営者はどういう人でどういう経営方針なのか、店舗数や近年の業績推移・従業員構成は、お客様にどういう傾向があるか、お客様にどんなところを指示されているのか、求職者にメリットを訴える。
・事業所登録シートの「会社の特徴」では、会社の長所を記載する。経営方針やミッション、社内の雰囲気や企業文化、教育研修制度、今後の事業展開などで魅力をアピールする。意欲の高い人はその会社で自分は成長できるかに大きな関心があるため社長の思いなどを訴えてもよい。
・「事業内容」はハローワークインターネットサービスで表示されるが、「会社の特徴」は表示されない。「事業内容」でより重要なことを述べ、「会社の特徴」では補足する内容としたほうが良い。
・職種の次に重要な「仕事の内容」は、収入よりもやりがい目的の発展途上人材を狙う。単に収入だけを重視する求職者は大手企業を目指す。
・求職者が入社後のシーンを思い浮かべられるくらいに仕事の内容を具体的に書く、仕事のやりがい・やりやすさが感じられる表現、求職者のメリットがわかるキーワードが必要。字数制限(297文字)いっぱい書く。
・「求人条件にかかる特記事項」(216文字)で職場特有の福利厚生や休み方、勤務体系等、極力求職者にとってメリットがある情報をまんべんなく伝えきる。休みが多い、子供が急病でも休みが取りやすい、勤務時間を変更しやすい、研修制度が充実、会社の費用でセミナーに参加できる等)
・「仕事の内容」は中小企業のサイズだからこそできる仕事、独自の売り、魅力を表現する。働き続ける魅力を訴えかける。ベテラン社員の従業員の声を入れる。
・ハローワークでは画像登録を利用する。(A4画像を10枚まで)職場風景、集合写真、求職者の不安感を払しょくできるもの、一日の仕事を説明するようなスライド、社長からのメッセージなども有効。
・ハローワークインターネットサービスの求人情報仮登録を利用する。(業務の効率化・コピペができる)
【求人票関係】
・求人情報を提供にチェック。自治体の求職コーナーなどにも公開される(求人情報広告業者から電話がかかってくるようになるが断ればよい)
・勤務シフトがある場合、求人票をシフトごとに分けて提出する
・福利厚生の一番人気は「借り上げ社宅」。都会ほどこの傾向は高まる。
・求人登録は、週末、連休の前日がねらい目(NEW扱いが長い)
・試用期間6ヵ月は長すぎ
・売り手市場では選考方法と期間はシンプルに短く。パートの募集で筆記試験はやめたほうがよい。(選考結果は2~3日後)
・書類選考、筆記試験は応募者が殺到している場合に設定。
・応募書類として履歴書、写真添付は良いが、ジョブカードや職務経歴書は本当に必要な場合のみに絞る。
・NGワードをやめる。
①「応募にはハローワークの紹介状が必要」
今現在働いていて、転職を考えている転職組は紹介状をもらう必要がない。採用後即戦力になる転職組は仕事を休んでハローワークに行く必要がありめんどくさくて避けてしまう。
②ハローワークからのお知らせ
求人票は雇用契約書ではありません、採用に際しては必ず労働条件通知書を交わし、賃金等の条件面を確認してください、など。ブラック求人に見えてしまう。
③質問はハローワークを通してください
④急募
この会社にはいつでも入れるからもっと条件の良いところを探してみようという気持ちになって逃げていく。
⑤(契)⑥直接の問い合わせはご遠慮ください。⑦アットホームな職場です、女性が多い職場です
・求職者にとってどんなメリット、得があるか、求職者に会社が何を与えられるか、求職者がこの仕事から得られる達成感、やりがいなど、求職者目線で具体的に表現されている必要がある。
・8割方の求人票は、表現が全体的に抽象的。具体的な記述が少なく、数字の裏付け根拠がなく信憑性に乏しい。言葉を飾っているだけの表現が多い。
・職種に勤務地を入れない
・「作業員」など蔑称と取られる呼び方を記載しない、加工作業など「作業」という記載をしない。
・採用後即出向など不安を煽らない。明確な理由を説明しておく必要がある。
・「誰にでもできる」と記載しない。まともに仕事を教えてくれないと読み取られる。
・トライアル雇用併用求人を利用しない。十分な教育体制があれば別。
・パート求人で「その他雑務」などあれもこれも感を出した記載は避けられる。
・画像情報(写真)があることを明記する。
・自社ホームページ(採用専用ページ)へ誘導する ・最後は「お気軽にお問い合わせください。」で締める

④できる人材がすぐに辞めない職場づくり
・人がすぐに辞める職場の共通点
①ニーズが満たされない
前職がある人であれば採用時に退職理由を聞き出し、職場でそのニーズが満たすことができないのであれば採用しない。
賃金や労働条件条件面以外にも、チャレンジングなことへの取り組みや仕事を通じて達成感を味わえる状態にすることが重要。
不安要素を排除してニーズを満たすとともに、働くことで自分が成長できると感じる職場にすること。
②人間関係が良くない
同僚の悪口を言う人と一緒に働くのは苦痛、上司がパワハラまがいの行為をする職場では働きたくない。
職場での人間関係を良い状態に保つには、まずはお互いについて詳しく知ることが大切。改めて自己紹介をする機会を作るのも一つの方法。
③会話がない
スタッフ間での雑談が必要。スタッフが働きやすい環境が作れる。相互理解が深まり、アイデアや気づきを気兼ねなく周りに伝えることができ、各自が持つ知識や情報が全体に共有されやすくなる。ANAでも雑談を推奨している。
④相談できない
真剣に仕事に取り組むがゆえに壁にぶち当たることがある。そのときに経営者や上司、先輩たちに相談できることが必要。月に1~2回程度、経営者・上司と部下が1対1で行う「個別ミーティング」がおすすめ。ミーティングの時間内に悩みがすべて解決しなくてもよい。次回のミーティングまでに自ら問題を解決してくるケースが多い。
⑤教育が足りない
教育が中途半端なまま新人に業務を任せてしまうとミスや失敗をする。これで叱られたりすれば理不尽さを感じる。
⑥関心がない
職場で上司や周りから無関心な態度を取られればモチベーションが下がる。ちょっとしたことでよいので積極的に話しかけることが必要。仕事ぶりをよく観察し、気づいたことをフィードバックする。
⑦将来が見えない
先輩らのやる気が低く、面白くなさそうに仕事をしている姿を目の当たりにすればそれを将来の自分に重ねて見てしまう。正社員の場合、自分より10歳以上年齢の人たちが、どう見ても幸せそうな生活をしていないと分かれば、将来に不安を感じて転職先を探し始める。
・辞めない人材は採用で8割決まる。頭数合わせの採用をやめる。
・採用後すぐやめてしまう大きな原因として、採用前後に感じるギャップの存在がある。
採用前後のギャップを下げるために、募集時に伝える9項目
①どんな人材が必要なのか
自社の社員として必要な人材はこんな人物という理想の人物像を具体化していく。
(ふさわしい行動、仕事に対する考え方、性格、価値観など)
②自社の説明は詳細に
開業してからの歩み、地域での役割、経営者の思いやビジョン、商品のこだわりなどを語る。
③仕事内容は漏れなく詳しく
こんな仕事までやらされるとは思っていなかった、とならないように。
④働く上でのメリット・デメリット
募集の段階で、働く上でのメリット、デメリットの両方を伝えておかないと、こんなはずじゃなかったと思ってしまう。
⑤既存社員・お客様の声
既に働いている人の言葉の方が説得力があり、心に刺さる。どんな人と一緒に働くことになるのか?、どういうお客様と接することになるのか?といった人に関する情報は応募者が最も気にする事項の一つ。
⑥1週間のモデル勤務パターン
自分の生活パターンがどうなるのか事前に分かれば、心理的ハードルが下がる。
⑦1か月働いたときに受け取れる賃金
パートであれば時給のみならず、モデル賃金(月収)も記載すると自分の生活がどうかわるのか分かるため応募に対する動機付けとなる。
⑧どう成長できるのか
人は自分が成長できると思える場で働きたいと考える。(存在の欲求、人間関係の欲求、成長の欲求:アルダファーのERG理論)
⑨受付時間
問い合わせ可能時間として任意の時間を明記しておけばしっかり対応できる。
⑶ 10月の消費税増税に向けて
この10月1日より消費税が増税される見込みです。増税に向けて変更契約書などの準備が必要なこともあるでしょう。5%から8%に消費税が増税された際と対応は基本的に同じですが、簡単におさらいします。
・消費税が8%か10%かは売手の基準に従う(9月30日出荷で8%請求なら仕入先の検収日が10月1日でも8%で計上)
・1年分の対価を前受し、中途解約時の未経過部分について返還しない契約で、継続して1年分の対価を受領した時点の収益として計上している場合は、9月30日までに収益として計上したものについてすべて8%を適用する。中途解約時に返還する契約では、原則通り10月以降分は10%が適用(税額差額請求する必要がある)。
・10月分の資産の貸付けの対価は10%が適用される。9月分を10月に受領すれば8%。
・貸ビルのオーナーが、電気等の供給を行う事業者から購入した電気等を販売する取引は、経過措置は適用されず、10月検針分でも10%。(電気供給業は10月検針分は経過措置により8%が適用)
・消費税率引上げに伴い,請負契約(2号文書)について,新たに課される消費税等相当額のみを増額する変更契約書を作成した場合、記載金額がない2号文書として200円の印紙税が課される。
・税額の差額請求をした場合、8%・10%ごとに「合計した税込対価の額」が記載されたものでなければならない。年間契約の請求書等は10月以降の対価の区分が必要(「区分記載請求書」の様式が必須)
・ 「工事の請負等に関する経過措置」の適用を受けた場合,取引の相手方に対して経過措置の適用を受けたものであることについて書面により通知をしなければならない。請求書等に経過措置の適用を受けたものであることを記載することでも認められる(経過措置通達22,31年経過措置Q&A(基)問27)。
②契約書の記載内容
主に変更契約の実務対応が行われるのは、工事関係、保守契約などの前受契約、住宅を除く建物賃貸借契約書だと思います。また施設の貸付とされる駐車場などの契約書も消費税が課税されるため変更する必要性があるかもしれません。(税込契約や消費税が明示されていないなら特に)
消費税増税の精算で揉めないためには、「その時点で施行されている法律に基づいた税率で消費税額の精算を行わせて頂くことになります。」という条項を入れておくことです。ただ事業者は、消費税転嫁対策特別措置法にて、転嫁拒否行為を禁止されていますので口頭でうまくいくことも多いでしょう。
また、賃貸借契約書では「契約期間の中途において消費税率の改定が行われた場合には、賃貸人からの通知の有無にかかわらず、消費税率改定後の賃料に係る消費税等については改定後の税率により計算するものとする。」などの条項を入れるのが良いでしょう。
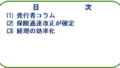
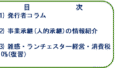
コメント