令和元年7月1日
本サイトの情報は、正確であるよう努めておりますが、万が一、情報が不正確であったことによる損害について、一切の責任を負いかねます。
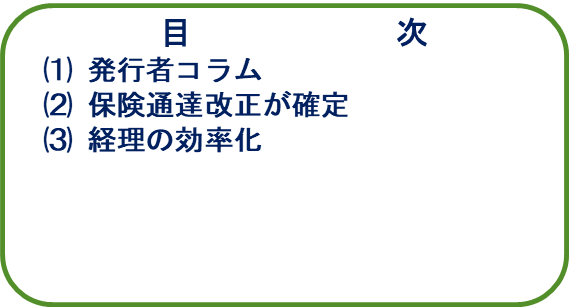
⑴ 発行者コラム
日経新聞(紙)を取るのをやめました。代わりに楽天証券の口座を無料開設して、スマホ&PCで無料で日々の日経新聞(朝刊・夕刊)を読めるようにしました。一面や総合などページ順に並んでいるのであまり違和感なく見れます。もちろん紙や日経電子版よりは見づらいですが、見出し+αの流し読みしかしていない私にはこれで十分でした。
有効求人倍率が全国1位~3位で推移している広島県。大手では、万能なツールではないものの2017年あたりからRPAを利用した業務自動化が進んでいるようです。プログラミングの知識が必要なく現場での開発が可能なため社内に広めやすいのだとか。中堅中小企業でも人手不足に対応するため、導入し始めている会社が増えてきているようです。利用料金も年間35万円程度~のものもあるようなので検討してみてはいかがでしょうか。ただ、業務フローの把握が必要だったり、自社でメンテナンスが必要なので完全に手間がなくなるわけではないようですが。AI導入のための1ステップとしてRPAが位置付けられており、大手はここを目指しているようです。
RPAの一つであるUiPathは、一定の条件を満たせば無料なので私も少しづつ勉強を始めました。ExcelVBA(マクロ)と合わせて勉強すれば効果的だと思います。人がいないので機械やシステム、クラウドサービス等にお金を払ってでも頼っていかないといけないのかもしれません。日本シェアNo1はNTTデータのWinActorらしいのでそちらを勉強してみてもよいでしょう。
⑵ 保険通達改正が確定(法人税)
①節税保険に対応した法人税基本通達が確定
メディアでも取り上げられ各保険会社が販売自粛している節税保険ですが、国税庁が封じ込めの通達を確定させたようです。
最高解約返戻率50%超の定期保険等は資産計上が原則になりました。税金の繰延のために加入する会社が多かった全額損金となっていた定期保険等が今後はほとんど資産計上となってしまうと考えて良いと思います。
本来の死亡保障等の保険機能を重視して保険加入を考えるようになりそうです。
②取扱い(新設:法人税基本通達9-3-5の2)
保険会社がよく解約返戻率の資料をつけていますが、今後はこの解約返戻率で経理処理が変わってきます。3区分に応じて保険料の一部を資産計上します。定期保険だけでなく、がん保険や医療保険などの第三分野保険の保険料もこの処理に統一されます。定期保険等の「等」というのは第三分野保険のことなんですね。
| 最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上額(残額を損金計上) |
| ①50%超70%以下 | 保険期間の前半4割相当の期間 | 当期分支払保険料×40% |
| ②70%超85%以下 | 当期分支払保険料×60% | |
| ③85%超 | 保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間の終了日 | 当期分支払保険料×最高解約返戻率×90%(or70%) |
また「保険期間が3年未満の定期保険等」や「最高解約返戻率70%以下、かつ、年換算保険料相当額が30万円以下の定期保険等」の保険料については,資産計上の必要はなく、損金計上することになります。少額の掛捨保険にまで資産計上は不要だということでしょう。今は存在しないでしょうが、保険期間が3年未満の節税保険が無理やり登場しそうな気もしますね。
解約返戻率が低すぎると、税金繰延の意味がなくなり単純に損するだけのため、85%前後の保険を選択することが多かったと思いますが、今後は60%~80%程度は資産計上することになってしまいました。多額の保険に加入すれば繰延は可能かもしれませんが、必要資金が多すぎて資金繰りが悪化してしまうため現実的ではないと思います。
③いつの契約から?遡るのか?
定期保険又は第三分野保険の保険料(下記保険料を除く):令和元年7月8日以後の契約分
解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険の保険料:令和元年10月8日以後の契約分
これ以前の保険契約に遡って上記通達が適用されることはありません。
⑶ 経理の効率化
①経理事務を効率化したい
中小企業、特に小規模な会社では経理事務を負担に感じていることが多いのではないでしょうか。経理効率化の手法について調べてみました。広島県は日本トップクラスの人手不足の県ですし。
②小口現金をやめて振込に キャッシュレス
(ⅰ)小口現金があると時間がかかる
社員の立替経費を現金で精算している会社は多いと思います。小口現金があると、仕事を止めて金庫番が出金作業を行ったり、領収書の整理を行ったり、現金残高を数えたり、現金出納帳を作成したり、上司が現金残高をチェックしたりと時間がとにかくかかります。時給2,600円の正社員がいたとして、小さな経費の精算を5分かけて行った場合、約216円のコストがかかっています。例えば、100円のボールペンを5分で小口現金精算すると316円でボールペンを購入していることになります。積みあがったら相当な額ですね。
(ⅱ)1か月分の経費精算申請書を提出してもらい、給与と一緒に振込
立替経費は1か月分の経費精算申請書をみな同じフォームで作成してもらい、給与と一緒に振込みましょう。通常、出張の多い人でなければ月1万円いかない人がほとんどです。
また経費精算申請書の勘定科目等も、申請者に記載させましょう。取引内容をよく知っている当事者が記載・集計するのがもっとも効率的です。使用する勘定科目は限られているはずですから、使用する科目の一覧表を一緒につけて運用してもらえば良いだけです。経費の科目が通常と少し違っていたくらいでは問題にはなりません。会社法や税法では、勘定科目名の指定はありません。
出張が多い人には、仮払制度をそのまま継続して、給与と一緒に仮払金も振込みましょう。精算して残金がある場合には、逆に会社の通帳へ振り込んでもらうのです。
(ⅲ)現金払いでないやり方を
会社が支払うものは、口座振替を利用するか請求書を発行してもらうようにします。キャッシュレスにするために、法人カードを利用するのも有効です(利用時の領収書等の証憑は適切に保管することが必要)。アスクルやAmazonで会社でまとめて注文して請求書をもらいましょう。
(ⅳ)現金商売の場合
1.レジには毎日定額のつり銭だけ残す、2.一日の現金売上は全額預金口座に入金する、3.仕入や経費はレジのお金で精算しない。小口経費は1か月分まとめて立て替えてもらって後日清算します。売上代金とレジが合わないのに、そこから経費の精算をしていたら合わせるのにさらに時間がかかります。今では、現金の計数機が売っていますから、買ってしまうのもアリだと思います。
③仕訳帳とは
青色申告法人は帳簿に所定の事項を記載しなければなりません(法人税法施行規則54条・規則別表20)。帳簿の種類としては,いわゆる仕訳帳と総勘定元帳その他必要な帳簿を設けなければならないこととされています。
このうち、仕訳帳について、必ずしも単一の仕訳帳を設けることを要するものでないから、例えば、個々の取引を現金出納帳、仕入帳、売上帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳等に記載し、その合計金額を一括して仕訳する方法によることもできる(旧昭25直法1―100「338」抜粋)とされています。
つまり、現金出納帳・売上帳・仕入帳なども帳簿になり、仕訳帳には科目別に一括合計転記すればよいことになります(ただ消費税の処理が異なるものはわけなければなりませんが)。現金出納帳を作成しているのに、また販売管理システムや購買管理システムを利用して売上高(売掛金・仕入高(買掛金)を個別に管理しているのに、会計システムへ入力する際にも、再び、売上、仕入や現金経費を相手先別に個別に入力していたりしていませんか?
④少額経費をまとめて計上
仕入以外の経費に関しては、原則としてそれぞれの取引を個別に帳簿に記載していくことになります。ただし、少額の経費はそれぞれその日々の合計金額のみを記載することができるものとされています。どこまでが少額なのか等、解説されているものは見当たりませんが、日々、科目別に少額の経費は合算して帳簿に記載して良いということになります。
例えば、小口経費精算を月1回まとめて行っているとして、電車代やタクシー代(同じ旅費交通費)がある場合には、これをわざわざ個別に分けて会計帳簿(現金出納帳等)に記帳する必要はなく、まとめて合計額を記帳すれば良いことになります(当然領収書等の証憑との紐づきは分かるようにしておかなければなりませんが)。ちなみに、消費税的にも、経費精算申請書に下記イ~ニまでの記載があれば問題ありません。経費精算申請書から二重転記していませんか?
帳簿への記載事項(法人税法施行規則 別表20)
(14) (13)に掲げるもの以外の経費に関する事項
賃金,給料手当,法定福利費,厚生費,外注工賃,動力費,消耗品費,修繕費,減価償却費,繰延資産の償却費,地代家賃,保険料,旅費交通費,通信費,水道光熱費,手数料,倉敷料,荷造包装費,運搬費,広告宣伝費,公租公課,機密費,接待交際費,寄附金,利子割引料,雑費等に,それぞれ適当な名称を付して区分し,それぞれ,その取引の年月日,支払先,事由及び金額。ただし,少額の経費で本文の規定により難いものについては,それぞれその日々の合計金額のみを記載することができる。
消費税法30条8項1号 仕入れに係る消費税額の控除
前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。
一 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行つた年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
消費税法基本通達11-6-1 仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例 抜粋
帳簿とは、第1号イからニ及び第2号イからホに規定する記載事項を記録したものであればよいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿でも差し支えない。
⑤支払日を月に1回にする
支払日が多いと、取引業者ごとに支払日を心配したり、支払い前の資金繰りの確認、振込データ作成、決裁者への申請や承認が必要になるため、時間がかかります。
会社の支払日を月に1回にするように変更します。支払条件があるところは変更をお願いしてみましょう。
⑥振込のために銀行に行かない
インターネットバンキングを利用しましょう。銀行への往復時間や窓口での待ち時間を考えるとかなりの時間を消費します。
月額口座維持手数料が気になる方は、ネット銀行を利用しましょう。ネット銀行は、月額口座維持手数料は無料なところがほとんどです。法人口座も開設でき、振込手数料も店舗型の銀行より安いです。イオン銀行や楽天銀行、GMOあおぞらネット銀行など、基本的に大手の上場会社グループが運営しています。もちろん1,000万円のペイオフも効きます。売上金の振込先がネット銀行だと嫌という方は、支払だけネット銀行を利用する手もあります。なお、ネット銀行の利用がどうしても嫌な方は、ゆうちょ銀行が2022年3月31日まで月額料金が無料になるキャンペーンを行っています。これ以降は総合振込のあるエキスパートプランで月額1,080円かかります。
令和元年10月から、市民税などの地方税の支払も「地方税共通納税システム」により手数料無料でネットで電子納税できるようになります(添付資料参照)。法人税や源泉所得税などもダイレクト納付という簡単な方法で電子納税できますが、地方税が電子納税ができなかったため結局銀行等に納付に行かないといけませんでした。これが無くなりほぼ全ての税金の支払が電子納税、口座振替で納付できるようになりました。
一番簡単で毎月発生する源泉所得税の電子申告・ダイレクト納付から始めてみましょう。源泉所得税の電子申告は、法人の電子証明書も必要ないのでコストもかかりません。口座を事前に税務署に登録しておくだけ利用できます。税務署もダイレクト納付を推進しています。
⑦預金口座を減らす
モノがあるとそれを管理する仕事が発生します。管理対象物を減らしていきましょう。預金口座もその一つです。預金口座を減らすと、預金口座間の資金移動の時間と手間が減り、口座の記帳をする手間と残高確認作業が減り、お金の流れもわかりやすくなります。
⑧銀行取引データや販売・仕入データを有効利用
インターネットバンキングを利用すると、銀行の取引取引データを会計システムに取り込むことが可能になります。銀行取引データの摘要などを事前に登録しておき仕訳をほぼ自動計上、またはAIを利用して仕訳を予測するというのが現在のトレンドです(もちろん合っているのか判断するには知識とメンテナンスが必要)。OCRのレベル向上により、請求書などをスキャンしてアップロードすれば仕訳計上してくれるクラウドサービス(STREAMEDなど)もあります。
また販売管理システムや購買・在庫管理システム、給与計算システムなどは、会計システムに取り込むための仕訳データをエクスポートできるようになっていることが多いです。(パッケージソフトであれば例えば、商奉行・蔵奉行から勘定奉行へ、弥生販売・弥生給与から弥生会計へ) 他の管理システムを利用しており仕訳が取り込めるのに、会計システムに手入力で転記していることがあり得ます。
⑨請求書を業者別・内容別に分類しない、ファイルを1つに
請求書や領収書を業者別や内容別に分類せずに、支払順にファイルすれば十分です。人間は、時系列の記憶力に優れているらしいので請求書も時系列に並べておけば良いようです。また、請求書は振込書類と一緒にファイルします。月別に支払ファイルを作成すれば良いと思います。
また、ファイリングはシンプルに、支払関係の書類はすべて1つにファイルすれば良いです。請求書も領収書も公共料金明細書も税金や社会保険の納付書も一つにまとめても全く問題ありません。
⑩勘定科目を統合して減らす
取引金額が小さい経費科目は、科目を統合して減らすことを考えます。勘定科目が多いと、それだけ判断に時間がかかり科目の分類に手間がかかります。金額が小さい経費科目は他の科目と統合するか、雑費に含めてしまいましょう。ただし、交際費や寄附金など税務申告書で金額を申告しなければならないものは分けておいた方が誤りが少なくなります。
なお、監査法人などの財務諸表監査を受けている会社は、注記が必要だったりするので注意しましょう。
⑪振替伝票はいらない(振替伝票は法定帳簿ではない)
振替伝票は法人税法で義務付けられている帳簿ではありません。会計システムが利用される前は、すべて手書きで帳簿を作成しており伝票会計であったため、振替伝票が利用されていました。この名残で、振替伝票を紙で起票してから自社の会計システムに転記していることがあります。
法人税法で作成が義務付けられている帳簿は、原則として、仕訳帳と総勘定元帳です(法人税法施行規則54条など)。会計システムは、データ入力されていれば、仕訳帳だろうが総勘定元帳だろうが、振替伝票でも一括して印刷できます。
内部統制やレビュー用にどうしても振替伝票が欲しいという会社は、会計システムに直接仕訳入力してから、印刷して利用することをお勧めします。
なお、仕訳帳と総勘定元帳は、法定帳簿であり所定の要件を満たしたうえで税務署に事前申請しない限り、印刷して紙で保存しなければなりませんので決算後に一括して印刷しましょう。(電子帳簿保存法)
ちなみに、スタンドアロンのパッケージ会計システムは、弥生会計など安いものであれば5万円しません。経理担当が1名の中小企業であればまずはこれで十分です。クラウド会計ソフトであれば年間2.5万円前後から利用できます。
⑫会計システムに会計処理を覚えさせる
会計システムは、標準的な仕訳パターンがあらかじめ標準装備されていたり、仕訳事例の検索して登録ができたりします。また会社独自の仕訳パターンも会計システムに登録することができます。毎月発生する旅費精算や給与支給といった取引を仕訳パターンとして登録しておけば、次からはそれをクリックして仕訳パターンを呼び出し、金額を変更すれば伝票入力が完了します。これにより簿記や税務の知識がほぼない人でもある程度の仕訳入力は可能かと思います。
仕訳入力に慣れている人でも、仕訳パターンを利用して入力したほうが作業時間は短くなるようです。積極的に利用しましょう。
⑬会計システムで補助簿までつける
会計処理と同様に多くの時間を割いているのが、補助簿の作成です。手書きやエクセルで別途作成していることがあります。売掛金や買掛金の管理は取引件数が増えると作業に時間がかかるため、販売管理システムや購買管理システムで管理しますが、取引件数が50件以下であれば会計システムでも管理ができます。
売掛金や買掛金の科目について、取引先名ごとに補助科目を設定します。この補助科目を使って仕訳データを入力することにより自動的に売掛金や買掛金の管理表が作成されます。これで回収・支払や未回収・未払残高の確認ができるようになります。預り金などの雑勘定も補助管理していないとあとで修正するのが非常に大変になります。
⑭考えないで仕訳入力できるようにパターン設定する
入力作業のほとんどは、通帳などの銀行取引データを見ながら行うことになるため、預金口座ごとに仕訳パターンを設定しておくと良いでしょう。
仕訳パターン名は、自分だけが分かる名前をつけるのではなく、例えば「NTTデンワ」などのように通帳に記載されているとおりに設定します。こうしておけば、次に誰が入力しても通帳を見ながら、仕訳パターンを探すことができます。仕訳パターンを登録する場合には、できるだけ人の判断が入らないようにするのがポイントです。
⑮合理化した時間で
総務・経理だけでなく、見積書の作成、請求書の発行、売掛金管理などの営業管理の仕事なども手伝ってもらいましょう。
プロジェクト別の業績管理、予算実績管理、資金繰り表の作成、給与計算、社会保険手続などできることはたくさんあります。
ただ、ルーチン業務しかやってこなかった人に、いきなり予算管理や資金管理を行わせようとするとうまくいかないようです。これらの仕事は、会社全体のことがわかっていないとできません。つまり他部門とのコミュニケーションがうまく取れる人材しかできません。
まずは、販売管理や購買管理、原価管理、在庫管理など他部門の業務から始めて少しずつ会社の理解を深め、徐々に予算管理や資金管理など会社にとって重要かつスキルレベルの高い仕事にシフトしていきましょう。
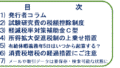
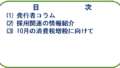
コメント