令和4年8月19日
本サイトの情報は、正確であるよう努めておりますが、万が一、情報が不正確であったことによる損害について、一切の責任を負いかねます。
⑴ 発行者コラム
畑に、防鳥網を追加で200坪張りました(白目)。元気な樹には、ブルーベリーの実が多くなりました。一部調子の悪い樹があり、冬場に水をやりすぎて根腐れしたんじゃないか、もしくは窒素のやりすぎ、という感じがあります。やはり自然相手は難しいです。日々経験、検証です。
JA福山のFUKUYAMAふくふく市に生産者として登録し出品してみたのですが、ライバルが多くて価格競争となり売れませんでした。(本当は尾道に出したいのですが、尾道市内の畑でとれたものでないとダメとのこと)
それならと、ジャムに加工して販売(要冷蔵・要冷凍)するには、保健所への届出が必要であるようで、食品衛生責任者の資格を取りました。資格を取るのに研修代として12,000円かかりました。ただジャムは収穫して調理して頑張って作って売れても1個数百円です。何を目指しているんでしょう(笑)
農業は販路が重要かつ難しいということが身に染みてわかりますね。

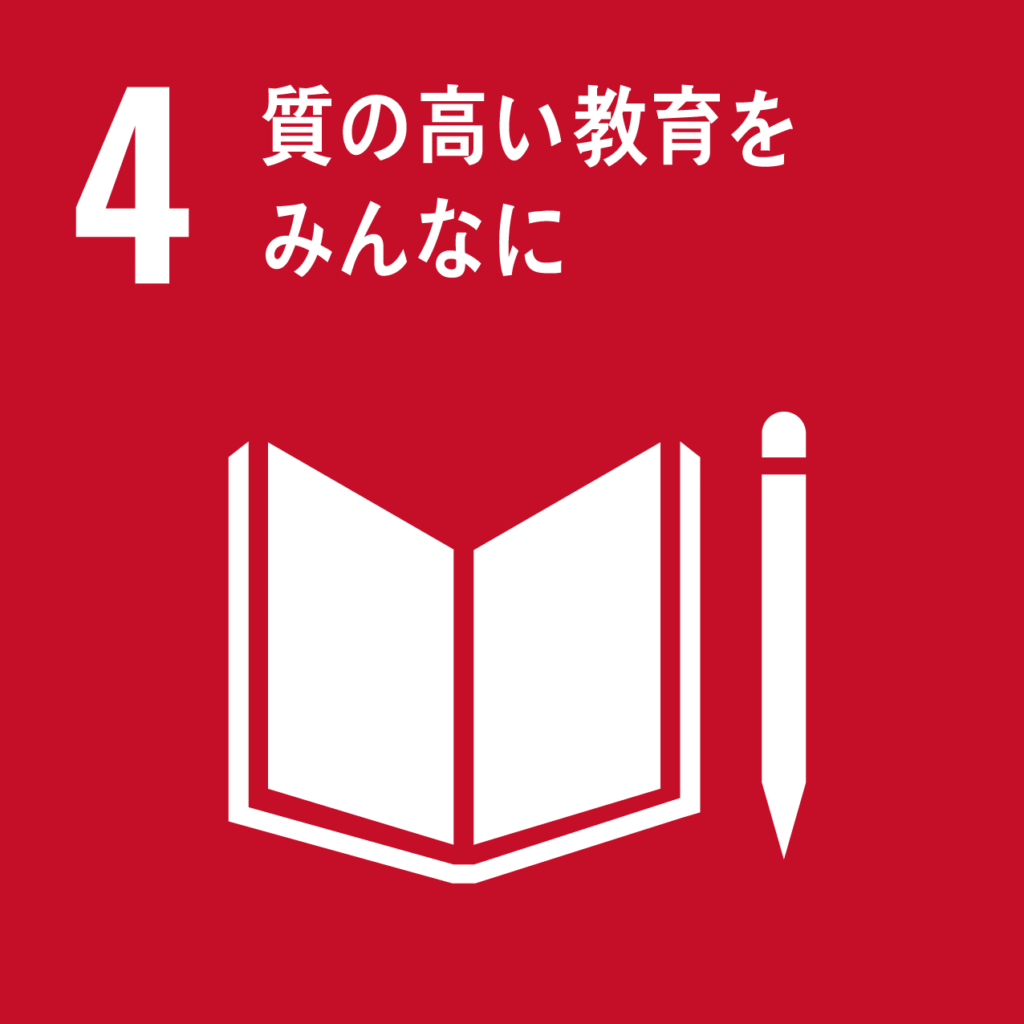
⑵ ㈱ひろしま事業承継パートナーズ
後継者不足・人材不足を背景に、事業承継関係業務のご相談・業務が増えてきたことに伴い、㈱ひろしま事業承継パートナーズと提携し、私、工藤が取締役に就任しました。広島・尾道・宇部に拠点を設けています。
㈱ひろしま事業承継パートナーズの代表(田島)は公認会計士であり、㈱日本M&Aセンターにおいて、コーポレートアドバイザーとして勤務して、企業価値の算定、財務内容の実地調査、グループ内組織再編(合併・分割・株式移転・株式交換等)、M&Aのスキーム提案などを行ってきました。
横文字が多いのでイメージがわきにくいかと思いますが、よく想定される案件としては、以下のようなものです。
・M&A譲受側が実施する財務デューデリジェンス(財務DD(監査))
・M&A仲介,FA会社のセカンドオピニオン業務(企業価値算定、契約関係の妥当性等)
・グループ会社整理のための合併や資産移転のための現物分配、複数後継者のための会社分割
一会計事務所では難しい業務になりますのでネットワークを活かして取り組んでまいります。事業承継やグループ内組織再編で、お困りごとがありましたらご相談ください。 本社: 〒732-0057 広島市東区二葉の里3-5-7 GRANODE広島3F
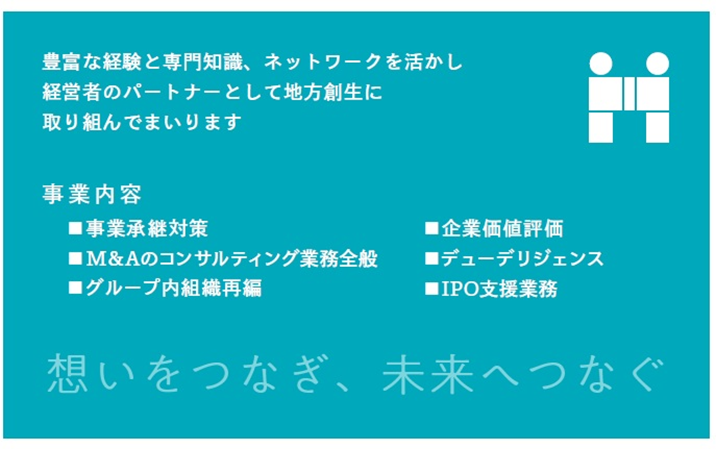
別途、「M&A成約までの流れ」を添付しています。例えば、譲受側の財務デューデリジェンスというのはどのタイミングでててくるのか等参考にしていただければ幸いです。
上場M&A仲介業者各社ご紹介できます(各社の特徴のご説明可能です)。なお、譲受側は事前に希望案件の話を具体的にしておかないと案件が出た際に紹介してくれません(ただ成約までに少なくとも1,000万円~2,000万円以上はかかります。)。手数料が厳しい場合は、ネットマッチングBATONZをご紹介します。

⑶ よくある質問(科目は〇〇でいいですか?)
よくある質問として、こうこうこういうものがあるのだが、科目名は何にしたらよいか?というのがあります。
結論から言うと、
税務上は、収益・費用・製造費用・資産・負債・純資産の大きい区分が合っていればなんでもいいですになります。会社計算規則にも具体的にこの科目名でなければならないという条文等はありません。(会社計算規則3条:この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。)
(税務上というのは、税務署に提出する決算書(とそれに関連する申告書類の)の作成方法のことだと思ってください。消費税の話は省略しています)監査法人等の会計監査を受けている会社や非営利の法人は各種の会計基準に従う必要があるため除きます。
なので、前は科目は何にしていましたか?〇〇でいいんじゃないですか?と逆に聞き返されてしまって不安になる人もいるのだと思います。
税法では、とある取引の計上科目をこういう科目名にしていないと絶対ダメだ、という規定はありません。もちろんウソはいけませんが。(なお、損金経理していないと認めないという規定は中にはあります。損金というのは≒費用のことです。損金経理というのは帳簿上費用計上していますかということです。)
例えば、販管費の中に、「法定福利費」という科目を使っている会社が多いと思いますが、この科目名称が「社会保険料」となってても良いですし、「会社負担の従業員の社会保険料」とかなってても良いです。(単純にカッコ悪いですけど)
また、例えば車輛費という科目をつかっていて、いつも車輛費に計上している取引を消耗品費に計上したからといって税務上は特に何もありません。経営管理上、前期比較や予算管理したときにブレが生じてしまいますが。
ウソや隠そうとしてさえいなければ、なんでもいいです。
税務上問題になるのは、各グループを超えている間違いです。例えば資産計上すべきものを費用に計上すればそれだけ利益が減って納税額が減りますから、誤りとして突っ込まれます。収益計上すべきものを負債計上していれば突っ込まれます。製造費用にすべきものを販管費の費用などにしていると仕掛品等への配賦額から漏れて突っ込まれます。
⑷ ビジネスカード(バクラク)
業務効率化のご支援をしていると、よく聞くのが、従業員の経費の精算に手間が生じているという内容です。(実は一番よくあるのは…、今お使いの販売・購買(在庫)管理システムに便利な効率化機能がすでに多く搭載されているのに、その機能を知らずそれを使っていない(業務フローをパッケージシステムに合わせるように変えていない)・初期設定をちゃんとしていないので使いたくても使えないケースです。次回以降の通信で記載していく予定です。)
対応するシステムとして、ジョブカン経費精算とかラクスの楽楽精算などを利用するという手もありますが、人数がある程度いると月額1万円以上にはなります。初期設定作業も必要です。
また精算するには証憑が必要であり、営業が写メをとっても電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件を満たせない場合は、この証憑(紙)を経理が収集してチェックする必要があります。
そして、経理精算システムを導入したとしても、営業が支払方法として会社支給の交通系ICカード等を使わない限り、各領収書を個別にシステムへ入力する手間が生じます。ただ、交通系ICカードですべて精算できるところはまだ少ないと思います。
そこで私が個人的にお勧めするのは、Bizプリカなどのビジネスカード(法人向けプリペイドカード)です。クレジットカード対応のところは、夜の飲食店以外は多いと思います。プリペイド式なので事前に管理者がチャージしないと使えないため変に使われることもありません。カードの利用情報があれば相手先と日付・金額が自動的にデータ化されcsvで取得できるため手記載、手入力するものが少なくなります。コピペ・加工もエクセルで一瞬でできます。バックオフィス業務の効率化を図るために重要なことは、いかに、現金など現物の管理対象を減らし、紙への記載、手入力、同じ情報の転記作業、を減らすことです。Bizプリカはこれを達成することが可能ですが、1枚月100円かかります。しかし月額無料のものが登場しました。バクラクのビジネスカードです。これから開始するサービスなので経費精算申請書を作るのに時間がかかって面倒くさい人は申し込んでみてください。



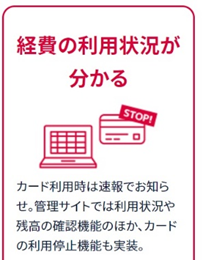

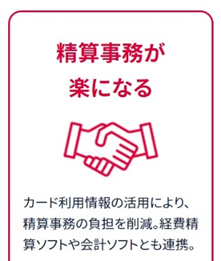
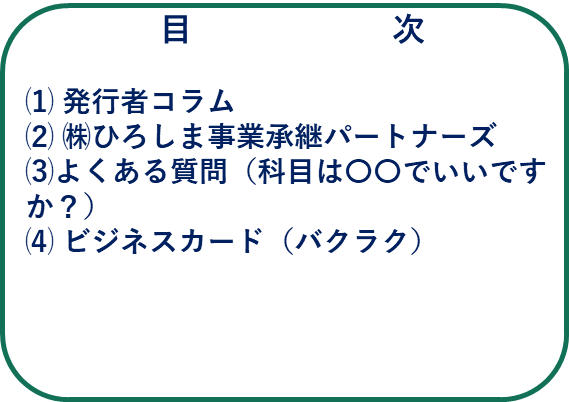

コメント