令和元年9月26日
本サイトの情報は、正確であるよう努めておりますが、万が一、情報が不正確であったことによる損害について、一切の責任を負いかねます。
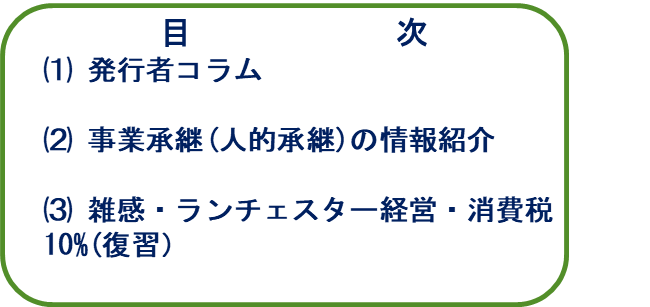
⑴ 発行者コラム
キャッシュレス・ポイント還元事業が始まりますね。2019年10月1日から2020年6月30日までです。対象店舗で対象となるキャッシュレス決済手段でお買い物すれば5%or2%のポイント還元が受けられるものですが、決済手段がなんでもいいわけではなく、お店ごとに決済手段が決まっていますので注意です。
尾道近隣だと、例えば、ひまわりが、VISA・MASTERカード、PayPay・LinePayとしていますね。ニチエー、MATEやアルゾなどの一部スーパーも対象店舗になっています。その他、コンビニ、ガソリンスタンドが還元率2%となっています。
で対象店舗が地図検索できますので検索してみてください。ついに我が家もようやくPayPayを登録する日が来たのですね。めんどくさいのでスルーしてました…。ひまわり、ニチエー、MATEで買い物をする方は是非対象決済手段を調べて電子決済しましょう。食品・日用品で5%は大きいです。ちなみに法人もポイント還元の対象です。
2019年10月といえば消費税のほかにも、地方税共通納税がありますね。これで住民税の納税のためだけに毎月銀行に行かなくて良くなります。PCdesk(Web版)またはCdesk(DL版)から口座登録を行えば、ダイレクト納付を利用できます。まずは口座登録をしてください。(源泉所得税もe-taxでダイレクト納付できます)
⑵ 事業承継(人的承継)の情報紹介
後継者不在の中小企業が多いです。私が最近読んだ本から自分なりにざっくりまとめた情報を共有します。
(1)人材選定で迷い続ける経営者たち
【新体制の発足が原因で会社が分裂する】
・ときに、法人に対する信頼よりも経営者個人に対する信頼が勝る。個人への尊敬の念は承継できないため、後継者が新たに信頼を築いていくしかないが、周囲にまだ新社長として認められていないうちから事業改革に着手したり、先代の路線を引き継がなかったりすれば、古参社員や従業員との軋轢が生じるリスクがある。抵抗勢力ができあがってしまえば、後継者の経営にとっての大きなマイナス要因になり、最悪の場合、会社が分裂する。
【後継者問題を後回しにせず急務の問題として考える】
・後継者の育成に必要な期間は、中規模企業では約半数、小規模事業者でも約4割が、事業承継には少なくとも5年以上10年未満の準備が必要であるという認識がある。 (中小企業白書2014年度版)
・「企業のパフォーマンスは経営者が60代でピークを迎え、70歳を超えると、稼ぐ力が低下する」(後継者問題に関する企業の実態調査・帝国データバンク)。企業の成長にブレーキをかけないためには経営者が60歳を超えたら事業承継の準備を始め、60代のうちに後継者を決定しておく必要がある。
【自分の分身をつくろうとすると失敗する】
・自分の分身をつくろうとすると、足りないところばかりが目につき、「彼は経営者には向いていない」などと悲観的に考えてしまう。一分野に並外れた才覚を見せる天才よりも、むしろ突出したものがなく能力のバランスのよい凡人のほうが、後継者として成功しやすく、事業承継もうまくいくことが多い。
・自分と異なる人格、異なる完成の持ち主である後継者に対して、いかに自分のノウハウや思いを伝えていくか考えるべき。
【理念や文化の承継】
・顧客を喜ばせ、満足させたり、より便利な商品を作り出したり、斬新なアイデアで新たな仕組みを生み出したりすることが大切であるのはいつの時代も同じ。その中にこそ経営者の理念やノウハウがある。経営者が長年にわたり蓄積してきた企業理念・文化やノウハウが、後継者にとって大きな財産になる。経営者はそうした理念や文化を後継者に伝えていかなければならない。
(2)事業承継を実現する
【経営者としてのタイプと役割を確認する】
・自分の人生の振り返り、それを会社と結び付け、自分が事業とどうかかわってきたか、どんな役割を果たしてきたのかを確認する。事業承継で重要なのは、自らがどんな経営者であったのかを客観的に分析すること。経営者のタイプはそのまま会社のカラーとなるものであるため、自らを知ることが会社のカラーを知ることになる。また自分が担っていた役割をクリアにすることで、後継者への引継ぎの際、相手との仕事上の得手不得手を考慮した最適な引継ぎ方法を選ぶことができる。
【経営者・後継者のタイプ分析】
外交的 or 内向的、直観的 or 現実的、柔軟的 or 規範的、独断的 or 合議的
このうち導き出される4つのタイプが会社のカラーにつながっていると考えられる。経営者・後継者それぞれをタイプ分析する。
【経営者・後継者の役割分析】
・どんな小さな会社にも、複数人で行う以上は必ず「業務分掌」が存在する。もし組織図があればそれを確認し、自分は組織のどのような業務に明るく、どのような役割であったかを考える。業務上の分担状況から、各部署への自分の介入度合いイメージすることで、自分がどのような職種寄りの経営者なのかが分かる。
あくまで現実に沿った形でタイプを判断すること。
①営業系
・直接営業職型(いわゆる営業)
・間接営業職型(テレマーケティングなど)
②営業支援系
・営業支援職型(商品企画・営業企画・広報など)
③専門技術系
・専門技術職型(研究・開発・プログラム・スーパーバイジングなど)
・一般技術職型(販売・配達など)
④管理系
・事務専門職型(財務・会計・経理など)
・一般事務職型(総務・受付・秘書など)
経営者・後継者それぞれを役割分析する。
【企業の中身をソフトとハードに分解する】
・企業の中身を「量や数字であらわせないもの」(ソフト)と「量や数値であらわせるもの(ハード)に分ける。
・親子間の対立や従業員の不満などといったソフトの要因から事業承継に失敗するケースが非常に多く、ソフトの部分をきちんと整えておくことも極めて重要である。
・企業のハード:資本金額、従業員数、売上高、取扱い製品など。
ソフト:経営理念、販売戦略、社長の個性、営業担当の性格など。
【引継ぎマニュアルを作成する】
①業務フローを明文化する
・業務の流れをフローチャートに落とし込むことで、自社の売上ができる仕組みを理解する。各部門の責任者に確認しながら、できるだけ細かく作ると、より引継ぎが円滑にできる。
②「自分のノウハウ」を明文化する
・事業承継は、感覚的な手法ではうまくいかない。自らが培ってきたものをできる限り明文化することで、後継者により正確に自分の意思が伝わる。まずは企業の理念や信念と、行動規則を書きだすこと。
企業理念とそれをどのように事業上体現しているか、信念とそれをどのように事業上体現しているか、記載する。
③「帳票・書式の見方」を明文化する
・帳票類や書式には、企業のノウハウが詰まっている。例えば、どんな製品を扱っているのか、製品をどのように処理するか、粗利が何%で利益がたつか、といった情報が帳票から読み取れる。これを明文化する。
④「組織図の考え方」を明文化する
・業務の目的と役割を明確にし、組織ごとの「目標予算(目的)」を「人員(誰)」が「何名:で行うのかを表しているものが組織図であり、この組織を編成した経緯と考え方を明確にすることで企業の理念が明確になる。例えば製品ごとの製造・営業までを一元化して管理する体系なのか、営業、製造といった業務ごとに分かれている体系なのかといったことを確認すれば、その企業の性質も分かる。
⑤「引継ぎ名簿」を作成する
・名簿は法人ではなくエピソードが具体的な個人について作成する。名簿を作る主な対象は以下の通り。
・社員名簿 ・仕入先、販売先といった取引先名簿 ・その他自分の人生に関わった人
【事業承継のパターン】
①ベンチャー型
法人の形態・屋号・事業内容を一新し、会社として新たに生まれ変わる引継ぎ方法
②匠型
仕事ができる幹部社員に事業を承継し、今までの路線をしっかり承継していく方法
③後見型
後継者に事業と人脈を少しずつ承継し、安定した経営ができるようになるまで見守っていく方法
④補佐官型
ある分野にだけ秀でた能力特化型人材が候補となった場合、足りない能力を補うために有能な補佐官をつけてから継承する方法
⑤戦略型
業務分野ごとに事業を分離して分社化し、それぞれがより利益を出せるように戦略を練って行う引継ぎ方法
⑥司令塔型
自らの強力なリーダーシップのもとで後継者を指名し、周囲の人間を納得させてえから行う引継ぎ方法
この中から、自分とその後継者、業務内容にマッチした引継ぎ方法を検討していく。
【両者の経営者タイプと職種タイプが同じ場合の最適な承継パターン】
自らの分身として、ソフトもハードも従来のものをきちんと継承することができるが、引継ぎ後に革新的な変革を起こすことは難しいかもしれない。幹部に十分に理解してもらい、引き続きバックアップしてもらうように引継ぎをすることが大切。
・司令塔型
経営者のカリスマ性が高いほど社内でも敬意を払われているため、後継者も従業員もその路線の継承を目指すことが多くある。そういうケースでは、経営者タイプと職種タイプが同じであることが効果を発揮する。
・匠型
自らの右腕といえる幹部社員に事業を承継し、今までの路線を継承していく手法で、経営者タイプと職種タイプが同じであれば申し分ない。
・後見型
経営者が安定した経営ができるまで育てつつ事業承継を行う手法を取る場合も、経営者タイプと職種タイプは同じであることが望ましい。どちらかのタイプが異なっていると、経営方針等の共有に時間がかかる。
【両者の経営者タイプが同じで職種タイプが異なる場合の最適な承継パターン】
思考パターンは同じだが、前経営者の職種タイプは会社の経営に色濃くあらわれるため、新たな経営者はその強みを生かせないことがある。それが売上に影響する可能性もあるので、そこをどのように穴埋めするか検討する必要がある。
職種タイプが異なると、前経営者の職種について想像できない可能性があるため業務内容について相互が理解できるまでじっくりと話し合っておくことが望ましい。
・司令塔型
職種タイプが異なっていても、経営者タイプが合っているならうまくいく。ポイントは、経営者が司令塔となって社内調整を積極的に行い、新体制になった際に弱点となる可能性のある分野を補強する体制をあらかじめ構築しておくこと。
・後見型
あらかじめ時間をある程度かけて引き継いでいく前提であれば、その溝を埋めることができる。
・補佐官型
職種タイプが違う場合、経営者が持っていた業務面での強みを新体制にいかに継承するかがポイントになる。後継者が一つの分野に秀でた能力特化型人材である場合は、それ以外の分野の力が大きく落ちてしまう可能性があるため、有能な補佐官を付ける必要がある。補佐官にそれなりの権限を与えたうえで、後継者は自分の得意分野に集中できる環境を用意する。
【両者の経営者タイプが異なるが職種タイプが同じ場合の最適な承継パターン】
経営者タイプが異なる場合は、思考パターンが違うことが経営方針にも影響を与えるため、売上の質が変わる可能性がある。もし現在の方針を維持してほしいなら、幹部社員なども交えて、今後の方向性を固めておく必要がある。ある程度の時間が必要となる。
・後見型
経営者タイプが異なり、性格の違う後継者に自分の思いを引き継ぐのは難しいが、職種タイプが同じであれば、事業承継はうまくいく。職種タイプに由来する経営手法において共通する部分があるので、経営者のカラーを残せる。
経営方針に関しては、相手が自分と違う考えの持ち主であることを十分に認識したうえで、多少の時間をかけて後継者を見守り、徐々に相手の理解を得ていく。ポイントは、自分と違うやり方であっても、いいものなら認めることで、互いのよい部分をミックスする意識で事業承継を行うと成功しやすくなる。
・補佐官型
経営者タイプが違ったとしても、職種タイプが同じであれば、補佐官型の事業承継も可能。後継者は自分と違った経営方針を打ち出す可能性が高くなるが、信頼の厚い補佐官にある程度の権限を与えておけば、万が一の暴走を抑えることもできる。
・戦略型
経営者タイプが違うと売上の質が変わることがあり、会社全体でそのリスクを負うことが難しいと感じるなら分社化という戦略を後継者には別会社として腕を振るってもらうという方法がある。もともとの会社の後継者には、自らと経営者タイプ及び職種タイプが近い従業員を選んで既存の路線をそのまま引き継ぎ、株式は自らが保有したまま会長職などに就くと良い。
【両者の経営者タイプと職種タイプが異なる場合の最適な承継パターン】
考え方も経営方針もまったく異なることが予想されるため、引継ぎ後には大幅な路線変更をする可能性が高くなる。もし自らが路線変更を望まないのであれば、後継者にはその核となる理念を十分に理解してもらわなければならない。その場合、あいまいな表現では理念が共有できないため具体的な約束を交わすことが必要である。また、引継ぎ後は自由にさせると決めたなら、完全に経営から身を引き、潔く口を出さないようにしなければならない。
・ベンチャー型
自らの路線を承継してもらうことにこだわりがない場合には、ベンチャー型の継承になることが多くある。後継者の個性を十分に発揮してもらうため、法人の形態や事業内容を一新し、新たに生まれ変わる。どうしても守ってほしいものがあれば、あらかじめ明文化して確約をとっておく必要がある。
・戦略型
全くタイプの異なる後継者に対し、自分の理念・文化の継承を望むのは極めて難しい。無理を押し付けて破綻するより、分社化して後継者に新たなステージを用意するほうがうまくいくことがある。分社化する場合、株式の委譲などを行って後継者が自由に動けるようにしなければならない。
【望まない継承パターンが適している場合】
判断は難しいが、「後継者の意識を変える」、または、「より適した別の人材を探す」という検討をするほうがおすすめ。
【その他引継ぎの注意点】
・職種タイプが異なる場合、もし後継者が自分の得意分野であるタイプに会社を強引に転換させようとすると争いが起こる。そうさせないためには、引継ぎの段階で経営者が差配すること。後継者が不得意な分野は、その分野は他の人材に思い切って任せてしまうほうがうまくいくことが多い。
・引き継ぐ人の敵になりそうな人物がいれば、先手をうって取り除く。
・営業系の経営者と技術系の後継者という構図がよくありがちだが、残念ながら多くの場合は事業承継はうまくいかない。
・経営者が思いや理念をあいまいにしたまま事業承継を行った結果、「こんなはずじゃなかった」と憤り、後継者や会社との関係が悪化するケースが多くある。どうしても伝えておきたい思いや理念は、明文化して後継者に渡し、理解、合意を得ておくのが重要なポイント。もしそれが業務に直接関係することは「今後何年の間は、Aという手法を変えないこと」というように具体的に約束を取り交わし、書面として残す。相手が自分と異なるタイプの場合、いくら口約束を交わしても相手の受け取り方が自分の意図と違えば、解釈が変わってくるからである。
・ベンチャー型の引継ぎは、社員の反発を想定して根回しすべし
・社内外に1人は経営について把握している人材をつくるべし
・ワンマン経営者こそより丁寧な引継ぎが大切、秘密主義は廃業につながる
・後継者は立場によって人格が変わることがある
・息子だからこそよけいに冷静に経営者タイプを判断すべし
・後見型では権限を一時期にすべてを預けぬこと
・後継者のタイプを読み誤らないように、第三者の意見も参考にすべし
・わが子可愛さで後継者の能力を判断する目が曇ることがある
・職種タイプとして、営業系から技術系への承継は難しいと知るべし
・後継者の苦手分野まで任せず、補佐官をつけて能力をカバーすべし
・職能的に優秀な人材でも、経営者として優秀かは分からない
・引継ぎ困難なら、外部から人を招くという選択肢も考慮すべし
・「兄弟げんか」が企業分裂につながることがよくある現実を知るべし
・兄弟であっても性格が合わねば共同経営は難しい
・わが子だから何でも分かった気でいると足元をすくわれることがある
・後継者が自分の意思を継いでくれるか、慎重に判断すべし ・分社化という手段が有効なこともあると知るべし
⑶ 雑感・ランチェスター経営・消費税10% (復習)
(1)雑感
前回採用関係の情報共有をしましたが、採用には時間もコストもかかります。時間とコストをかけても採用できるとは限りません。育成にも時間がかかります。採用してすぐ退職するかもしれませんし、人の意識は簡単に変わるものではありません。今後も人口は減少し続け、人手不足感が中小企業まですぐになくなるとは思えません。資本力のある大手は違うのでしょうが。
個人的には、中小企業は業務プロセスを見直して無駄(不必要不効率な業務)を排除して業務担当の再編をしたり、機械化、AI・RPA、各種クラウドサービスを利用して各業務プロセスを標準化・効率化したほうが早いような気がしています。現状ある程度の規模のある中堅企業はまだ別として、小規模な会社はもし全体の売上が下がってしまったとしても、自社の相対的に優秀な人材が疲弊して流出するよりは、企業全体の労働生産性(1人当たり・時間当たり)が上がればよい、そういう考え方が特に必要になって来ている気がしています。
(2)ランチェスター経営
ご存知の方は多いかと思いますが、採用ができない中小企業に特に合致すると個人的に感じる弱者の戦略です。
①差別化 弱者は、強い会社と違うことをする
②小さな一位 弱者は、小規模一位、部分一位。何かで一位
③一点集中 弱者は、あれこれしない。1つに絞る
④接近戦 弱者は、エンドユーザーに直接営業する
①差別化
強い敵とは戦わない、強いライバルが少ない市場を選ぶ。市場・商品・地域・客層・営業方法を差別化する。どんな業界でも、大手との差別化と細分化と一点集中でニッチなすき間市場が見つかる。一定数の顧客に支持される市場があることを前提に、どこにもない商品を、誰もやっていない売り方で差別化する。
商品差別化の例:手作り(めんどくさい系)、少量生産、オーダーメイド、市場が小さい、衰退産業、イメージが悪い
②小さな一位 ③一点集中
「深く穴を掘れ。穴の直径は自然に広がる」。「何でもします」は、顧客から見ると何が得意なのかがわからず、専門分野がないように映る結果、仕事が来ない。専門特化すると相手から覚えられやすくなるから、口コミや紹介が出やすい。ナンバーワンは人に覚えられるが、ナンバーツーは覚えられない。
業界の中で単価が低く、カッコ悪く、手づくり・めんどくさい系の仕事はないか?という視点で見る。高効率・大量生産に向かない仕事は、粗利が高いにもかかわらず、業界大手は見向きもしない。
④接近戦
エンドユーザーへの直販を行う。弱者はお客と離れて大量販売的にやるのではなく、エンドユーザーと直接触れ合う接近戦をやる。ライバルよりも、お客に近づく。ハガキ、メルマガ、ニューズレター、フェイスブックなどのアナログ営業を行う。ザイアンスの法則(人は、知らない人には攻撃的で、警戒心を持つ。接触回数に比例して好意を抱く。相手の人間的な側面を知ると親近感を持つ。)を利用する。
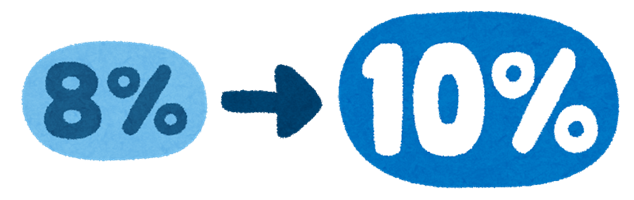
(3) 消費税10%(復習)
・例えば、20日締めの場合、9月21日~30日の請求書と10月1日~10月20日までの請求書は、売上も仕入も分けて発行してもらう必要がある。
・売上代金を前受で一括収受している場合、中途解約で返金が生じるなら、8%一括処理は不可。(10月分から10%で請求必要)
・10月以降に引渡になる工事契約。中間金は中間金に過ぎないので、8%で支払っていても、最終引渡しの時期が10月以後なら、10%税率で全体精算が必要。
・軽減税率8%(食品等)は8%据え置きではない。消費税率マスタは別々になる。販売・購買・会計等のソフトウェアのアップデートをお忘れなく。
軽減税率対策補助金をお忘れなく
9月30日までに軽減税率対応レジ の設置・支払いが完了したものを補助対象としていましたが、9月30日までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していることを対象要件とするよう各種規定が改められました。これにより、9月30日以降に設置・支払いが行われるものも本補助金の対象となります。「軽減税率対策補助金の手続要件を変更します」 https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190828004/20190828004.html
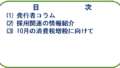
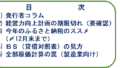
コメント