令和3年6月28日
本サイトの情報は、正確であるよう努めておりますが、万が一、情報が不正確であったことによる損害について、一切の責任を負いかねます。
インボイス制度について ③
前回、前々回とインボイス制度についての情報をお届けしました。今回はまとめとして、インボイス制度導入にあたり「パターン別検討すべきポイント」を、簡単に記載していきたいと思います。
(パターン1)
⇒ 消費税の課税事業者であり、今後も継続して課税事業者である
適格請求書発行事業者の登録を行い、要件を満たした様式の請求書を交付できるよう準備を進める必要があります。現在、複写型の請求書等を他社から購入して利用されている場合には、インボイス制度移行後に流用できなくなる可能性もあるため、過剰在庫とならないよう注意してください。
また、取引の相手方に免税事業者がいないかどうかをできる限り調査し、インボイス制度が始まるまでに適格請求書発行事業者(課税事業者)の登録を依頼することも重要です。
(パターン2)
⇒ 現在まで継続して免税事業者である
免税事業者のままでは適格請求書が発行できないため、取引の相手方は仕入税額控除ができなくなります。そうなると、取引関係が維持できなくなる可能性も発生します。これを踏まえて、今後も免税事業者であり続けるのか、適格請求書発行事業者として課税事業者となるのか、どちらかの選択を早めに行う必要があります。
また、課税事業者となった場合、納税額がどの程度経営に影響するのか検討しておくことも重要です。
(パターン3)
⇒ 年度により、消費税の課税事業者と免税事業者を往来する
パターン2記載の理由から、適格請求書発行事業者の登録を行い、継続して課税事業者となる形が良いと考えます。
◎担当者コラム
適格発行事業者の登録には、一定の審査期間が設けられるそうです。そのため、令和5年10月1日のインボイス制度開始と同時に対応するためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。インボイス制度の開始が近づくと、税務署に多くの事業者が訪れ混雑すると予想されるため、早めの準備をお願い致します。
国税庁が「インボイス塾」と題した研修動画(全4回)を、YouTubeにアップロードしています。弊所よりお伝えしてきた情報ともリンクする内容になっておりますので、よろしければご視聴ください。


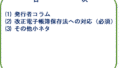
コメント